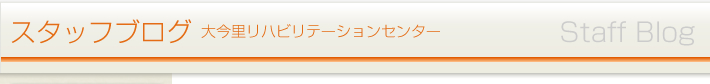2009年1月 5日
日本の四季の中で育まれた『節句』
日本には豊かな四季の中で育まれた多くの「節句」があります。
この節句は、もともと奈良時代に中国から伝えられた風習とのこと。
それを稲作を中心とした当時の日本人の生活のリズムにあわせたことから、節句は日本の季節行事として深く根を降ろし、現代に至っています。
昔はたくさんの節句があったようですが、このうち現代に伝わる五節句は、江戸時代に幕府がそれまでの節句をもとに公的な祝日として制定したものです。
五節句には、3月3日、5月5日のように奇数の重なる日が選ばれていますが、この考えも中国から伝来した影響です。ただし1月だけは1日(元旦)を別格とし、7日の『人日(じんじつ)』を五節句の中に取り入れています。
『人日(じんじつ)』と言うより『七草の日』の方が皆さんには馴染みが深いと思います。
この他の五節句にも、3月の上巳(じょうし/じょうみ)の桃、5月の端午(たんご)の菖蒲、7月の七夕の竹、そして9月の重陽(ちょうよう)の菊と、必ず季節の草や木に彩られるのが特徴です。
節句にはそれぞれ独自の意味がありますが、いずれもその季節に見合った供物を神に捧げ、のちに人々がその供物を共に食べたり飲んだりする点は共通しています。
「節句」が「節供」とも書かれるのもこれに由来しているようです。
昔の人々にとって、節句は一種の民間の神事であると同時に、祈りを共有することで人々の絆を深める行事でもあったようです。
また、日常の雑事を忘れて身体を休め、日頃あまり口にできない滋養のあるものを食べて鋭気を養う貴重な機会でもあったようです。
2009年1月 7日
五節句の一つ 『人日』

五節句の一番最初、『人日(じんじつ)の節句』は、「七草」として知られている1月7日です。
この日は昔、中国には元日から六日までの各日に、獣畜をあてはめて占いを行う風習がありました。元日には鶏を、二日には狗(いぬ)を、三日には羊を、四日には猪(いのしし)を、五日には牛を、六日には馬をというように占っていき、それぞれの日に占いの対象となる獣畜を大切に扱いました。そして新年七日目は、人を占う日にあて、これを人を大切にする「人日(じんじつ)」という節句としました。またこの日は、七種類の若菜を入れた温かい吸い物を食べて一年間の無病息災を祈る日でした。
現代にまで伝わる、1月7日に七草粥を食べるという風習は、もともと日本にあった、七種類の食材で作った粥を食べて健康を願う風習と、正月に若菜を摘む風習とが、中国から伝わった「人日(じんじつ)」の風習と混じり合って、人々の間に根づいたものです。
2009年3月 8日
桃の節句(雛祭り)
ご存知ですか?
雛祭り(ひなまつり)
5節句の1つで、3月3日に行われる上巳(じょうし)の節句に、女の子のいる家庭で、雛人形やその調度類を飾り、白酒・菱餅・あられ・桃の花などを供えて祭る行事です。「雛節句」「桃の節句」とも呼ばれ、女の子の健やかな成長を願う祭りです。

古く中国では農作物をつくる上で重要な季節の3月に禊(みそぎ)をして穢れ(けがれ)を祓う(はらう)習慣があったそうです。
中国から移入され、日本でも3月に穢れ(けがれ)を祓う(はらう)ようになり、家々で手作りした質素な人形や衣類を、人々の身代わりに災厄(さいやく)を人形に託し、川や海へ流していたのが上巳(じょうし)の節句の始まりと言われています。
これを流し雛といい、現在も鳥取県用瀬町の流し雛は有名です。
それがやがて精巧な美しい雛人形となり、いまに伝わる雛祭りへと発展していきました。また雛飾りには欠かせない桃の木は、古代中国では邪気を払う仙木(せんぼく)と考えられていました。
桃の葉もまた、浴そうに入れ、汗疹(あせも)やただれに効き目があると言われ、古来より用いられていました。「桃」はどうやら、暮らしのなかに息づいていたようです。
いずれにせよ、何げない供えものの中に、娘が健やかに育つようにと願う心があらわれています。

最上段に飾られる女雛と男雛は、内裏雛(だいりびな)あるいは親王(しんのう)雛などと呼ばれます。その飾り方は、土地柄によって異なるようですが、もっとも大きな違いは、京都など古い土地柄で行われる古式(向かって右が男雛)と、昭和以降、昭和天皇のご即位の方式にならった現代式(向かって左が男雛)ではないでしょうか。
雛人形を飾る上では、どちらを採用しても良いそうです。
2009年3月21日
『ぼたもち』と『おはぎ』の違いって何?
太陽の中心が春分点(天球上の赤道を太陽が南から北へ横切る瞬間の交点)に達し、全地球上の昼と夜の長さがほぼ等しくなる日には『春分の日』と『秋分の日』がありますね。
『春分の日』を境にしては夏至まで昼間が徐々に長く、夜が短くなります。一方、『秋分の日』を境にして冬至まで昼間が徐々に短く、夜が長くなることはご存知ですよね。
この時期によく食べるものとして、『ぼたもち』や『おはぎ』がありますが、その違いってご存知ですか?

実は、『ぼたもち』と『おはぎ』は基本的に同じもので、違うのは食べる時期が違うだけなんですね。
これらを漢字で書くと『牡丹餅』と『御萩』となります。
つまり、牡丹の花が咲く季節に、神仏や先祖への供物とされた小豆餡を、牡丹の花に見立てたことから、春の彼岸に食べるものを『ぼたもち』と呼び、同様に小豆餡を秋の彼岸の時期に咲く萩の花に見立てたことから『おはぎ』と呼ぶようになったとのことです。
現代ではほとんど使われていませんが、夏の季節に食べるものを『夜船』と呼び、冬の季節に食べるものを『北窓』と呼ぶそうです。
そもそも『ぼたもち』も『おはぎ』もお餅と作り方が異なり、「ペッタン、ペッタン」と音を出さずに作ることができるので、隣人には、いつ搗いたのか分からないことから、言葉遊びとして呼んでいたとのこと。
夜は暗くて船がいつ着いたのかわからない、ということから
「搗き知らず」→「着き知らず」 で『夜船』と呼ぶようになり、
月を知らない、つまり月が見えないのは北側の窓だ、ということから
「搗き知らず」→「月知らず」で 『北窓』と呼ぶようになったそうです。
今では、『ぼたもち』も『おはぎ』も区別なくつかっていますが、このような由来があったのですね。