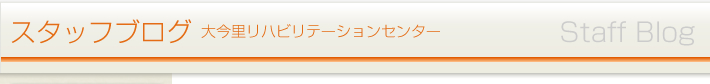太陽の中心が春分点(天球上の赤道を太陽が南から北へ横切る瞬間の交点)に達し、全地球上の昼と夜の長さがほぼ等しくなる日には『春分の日』と『秋分の日』がありますね。
『春分の日』を境にしては夏至まで昼間が徐々に長く、夜が短くなります。一方、『秋分の日』を境にして冬至まで昼間が徐々に短く、夜が長くなることはご存知ですよね。
この時期によく食べるものとして、『ぼたもち』や『おはぎ』がありますが、その違いってご存知ですか?

実は、『ぼたもち』と『おはぎ』は基本的に同じもので、違うのは食べる時期が違うだけなんですね。
これらを漢字で書くと『牡丹餅』と『御萩』となります。
つまり、牡丹の花が咲く季節に、神仏や先祖への供物とされた小豆餡を、牡丹の花に見立てたことから、春の彼岸に食べるものを『ぼたもち』と呼び、同様に小豆餡を秋の彼岸の時期に咲く萩の花に見立てたことから『おはぎ』と呼ぶようになったとのことです。
現代ではほとんど使われていませんが、夏の季節に食べるものを『夜船』と呼び、冬の季節に食べるものを『北窓』と呼ぶそうです。
そもそも『ぼたもち』も『おはぎ』もお餅と作り方が異なり、「ペッタン、ペッタン」と音を出さずに作ることができるので、隣人には、いつ搗いたのか分からないことから、言葉遊びとして呼んでいたとのこと。
夜は暗くて船がいつ着いたのかわからない、ということから
「搗き知らず」→「着き知らず」 で『夜船』と呼ぶようになり、
月を知らない、つまり月が見えないのは北側の窓だ、ということから
「搗き知らず」→「月知らず」で 『北窓』と呼ぶようになったそうです。
今では、『ぼたもち』も『おはぎ』も区別なくつかっていますが、このような由来があったのですね。