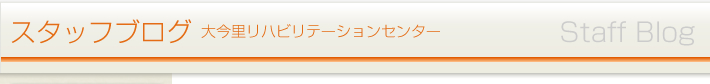日本の四季の中で育まれた『節句』
日本には豊かな四季の中で育まれた多くの「節句」があります。
この節句は、もともと奈良時代に中国から伝えられた風習とのこと。
それを稲作を中心とした当時の日本人の生活のリズムにあわせたことから、節句は日本の季節行事として深く根を降ろし、現代に至っています。
昔はたくさんの節句があったようですが、このうち現代に伝わる五節句は、江戸時代に幕府がそれまでの節句をもとに公的な祝日として制定したものです。
五節句には、3月3日、5月5日のように奇数の重なる日が選ばれていますが、この考えも中国から伝来した影響です。ただし1月だけは1日(元旦)を別格とし、7日の『人日(じんじつ)』を五節句の中に取り入れています。
『人日(じんじつ)』と言うより『七草の日』の方が皆さんには馴染みが深いと思います。
この他の五節句にも、3月の上巳(じょうし/じょうみ)の桃、5月の端午(たんご)の菖蒲、7月の七夕の竹、そして9月の重陽(ちょうよう)の菊と、必ず季節の草や木に彩られるのが特徴です。
節句にはそれぞれ独自の意味がありますが、いずれもその季節に見合った供物を神に捧げ、のちに人々がその供物を共に食べたり飲んだりする点は共通しています。
「節句」が「節供」とも書かれるのもこれに由来しているようです。
昔の人々にとって、節句は一種の民間の神事であると同時に、祈りを共有することで人々の絆を深める行事でもあったようです。
また、日常の雑事を忘れて身体を休め、日頃あまり口にできない滋養のあるものを食べて鋭気を養う貴重な機会でもあったようです。